

春秋彼岸とは、日本の伝統的な供養の期間であり、春彼岸(3月)と秋彼岸(9月)の年に二回訪れます。
これらの期間は、中日(春分・秋分の日)を中心に前後3日を加えた計7日間で構成され、彼岸会と呼ばれる法要が営まれる事もあります。
この時期は昼間と夜間の時間がほとんど同じになって来るので、仏教では「この世(此岸)」と「あの世(彼岸)」が最も近づく特別な時とされます。
私達日本ではそれらの日を春分と秋分の日を起点として、それぞれ7日間行われます。
仏壇やお墓を綺麗にしてお供えを行う習慣があります。
しかし、近年では家族が遠方に住んでいる事や、高齢で移動が難しいといった理由から、従来の対面での法事が困難になるケースが増えています。
そうした背景の中で注目されているのが、オンラインで行う法事です。
インターネットを活用する事で、自宅にいながら家族や親族と共に春秋彼岸のオンラインの法事ができる新しいスタイルが広がりつつあります。
本記事では、春秋彼岸にオンライン法事を行う方法について詳しく解説し、準備の仕方や進行のポイントを紹介します。
伝統的な供養の心を大切にしながら、現代のライフスタイルに合った形でご先祖様を偲ぶ方法を見つけてみましょう。
春秋彼岸とは?

春秋彼岸とは、日本の仏教における伝統的な供養の期間であり、春彼岸(3月)と秋彼岸(9月)の年に二回訪れます。
これらの期間は、春分、そして秋分の日を起点にそれぞれ前後3日を含めた1週間で構成されます。
この時期は昼間と夜間の時間がほとんど等しくなる為、仏教では「この世(此岸)」と「あの世(彼岸)」が最も近づく特別な時とされています。
春秋彼岸の違いと供養の仕方
春彼岸と秋彼岸の違いは、基本的には季節の違いによるものです。
どちらもご先祖様を供養し、日々の感謝の気持ちや想いを伝えていく大切な行事ですが、それぞれの時期の気候に合わせた供物や行事が行われます。
春彼岸(3月)
中日が春分の日。暖かくなり始める季節です。
お参りの際に桜の花や春の花を供える事が多い。
定番の供物として「ぼたもち」や季節の果物を供える。
秋彼岸(9月)
中日が秋分の日。涼しくなり始める季節。
定番の供物として「おはぎ」やせんべい(小倉山あられなど)を供える。
落ち着いた季節柄、ゆっくりと供養をする家庭が多い。
供養の重要性と、家族で行う意義
春秋彼岸のオンラインの法事は、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えていく大切な機会です。
仏壇やお墓を清め、お線香をして、故人を偲ぶ事で、家族の絆を改めて確認していく事が出来ます。
また、親から子へと供養の習慣を伝えていく事で、先祖を敬う心を後世に受け継ぐ事にもつながります。
最近では遠方に住んでいる家族や、高齢のために外出が難しい方々が増えている事から、オンライン法事を活用する家庭も増えています。
時代とともに供養の形が変わっても、ご先祖様を思う気持ちは変わらず大切にしていくのがベストです。
【春秋彼岸をオンラインで法事】という新しい形
最近では、遠方に住む家族や高齢の方の負担を軽減するために、オンライン法事が注目されています。
インターネットを活用する事で、住職の読経を遠隔でお願いし、ご自宅にいながらでも参列出来ます。
また、WEBを活用すれば、合同の法要や個別の法要も可能です。
春秋彼岸のオンラインの法事、基本的な流れ
オンライン法事は、従来の法事と基本的な流れは同じですが、オンラインならではの準備や進行方法が必要になります。
1.事前準備
日程の決定:家族や親族が参加しやすい日を決める(春秋彼岸の期間内)
参加者への案内:Zoom、YouTubeライブなどのリンクを送る
僧侶(住職)の手配:希望する宗派の僧侶を予約する
香典・返礼品の準備:参加者に香典をいただく場合は、表書きや封筒を用意
2.僧侶の手配(必要に応じて)
僧侶にオンライン読経を依頼する(ZoomやYouTubeを通じて法要を配信)
オンライン対応の寺院や法要サービスを利用する
3.法要の進行
僧侶による読経(事前録画でも可)
画面越しにお焼香を行う
家族それぞれが画面越しに焼香を行う
故人の思い出を共有し、祈りを捧げる
4.法要後の交流
オンライン座談会を開き、思い出を語り合う
供膳やおはぎ、あられ(せんべい)などを準備し、お供えと共にいただく
参加者で故人の思い出を話し合う
写真や動画を共有する事で、家族のつながりを深める
後から録画を視聴できるようにする
ZoomやYouTubeライブなどの活用
オンライン法事には、ZoomやYouTubeライブを活用すると便利です。
Zoom:家族だけで行う少人数の法事に適しており、リアルタイムで会話しながら進行できる。
YouTubeライブ:寺院の僧侶が読経を配信し、家族は各自の場所から視聴しながら参加できる。
LINEビデオ通話:親族が少人数の場合、手軽に使えるツールとして有効。
どの方法を選ぶかは、参加者の人数やインターネット環境に応じて決めるとよいでしょう。
遠方の親族が気軽に参加できるメリット
春秋彼岸のオンラインの法事は、以下のようなメリットがあります。
✅遠方の家族も参加しやすい(移動の負担なし)
✅高齢者や体調が優れない方でも自宅から供養できる
✅仕事や育児で忙しい人も参加しやすい
✅交通費や宿泊費を抑えられるため、経済的な負担が軽減
✅後から録画を見て供養する事も可能
オンライン法事は、現代の生活スタイルに合わせた新しい供養の風習として、今後さらに広がる事が予想されます。
特に、3月17日から始まる春の彼岸や秋の彼岸の時期に、オンラインで家族が集まり、ご先祖様に感謝を伝えていく事は、伝統的な供養の意味を大切にしながら、新しい形で供養を行う方法の一つといえるでしょう。
オンラインで春秋彼岸の法事をするメリット

近年、インターネットを活用した法事の種類が増えており、春秋彼岸のオンラインでの法事を行う事で、多くの家族が無理なく参加できるようになりました。
家族がどこからでも参加可能
オンライン法事を活用する事で、遠方に住む親族や海外在住の家族も簡単に参加して頂けます。
また、電話やFAXを使って法要の詳細を事前に確認できるため、オンライン環境に不慣れな高齢者も安心です。
移動コストの削減
通常の法事では、親族が集まるための交通費や宿泊費が必要ですが、オンライン法事なら価格を抑えつつ供養を行う事が可能です。
感染症対策としても有効
オンライン法事なら、直接対面せずに供養ができるため、健康リスクを減らせます。
オンライン配信を記録できる(後で視聴可能)
法事の録画を残す事で、当日参加できなかった方も後日供養の様子を確認可能です。
春秋彼岸、オンラインの法事のやり方
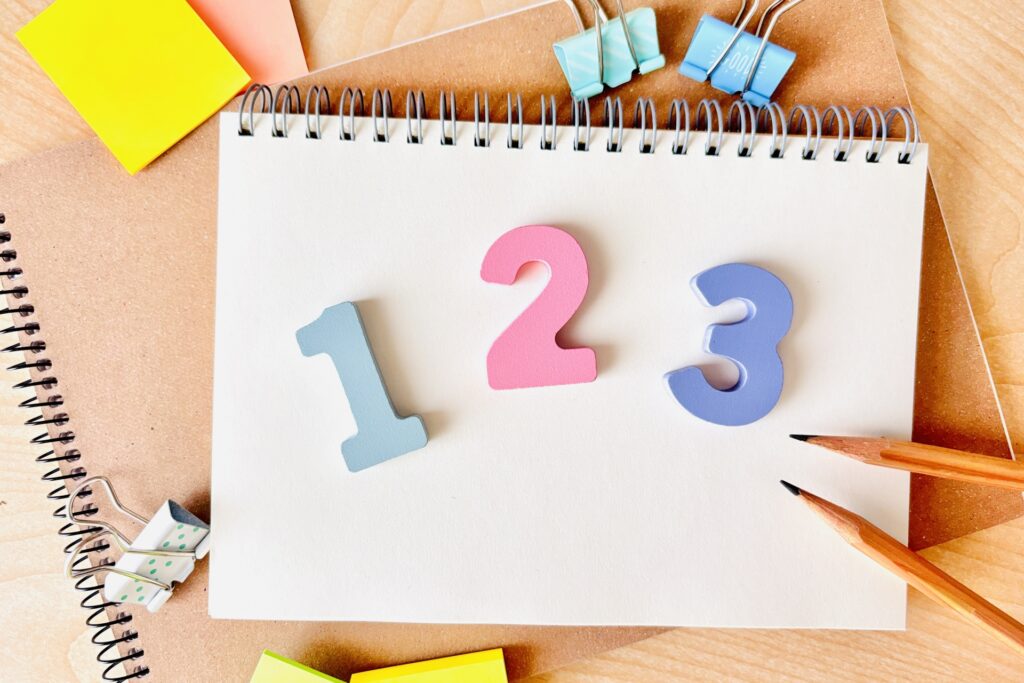
春秋彼岸のオンラインの法事をオンラインで行うには、準備とスムーズな進行が重要です。
以下の手順を参考にしてください。
準備するもの
【1.パソコンやスマホ、タブレット】
画面が大きいデバイスのほうが見やすく、安定した通信が可能です。
【2.Zoom、Google Meet などの配信ツール】
✅Zoom:招待リンクを共有しやすく、多人数の参加に適している。
✅Google Meet:Googleアカウントを用意すればすぐに利用可能。
✅YouTubeライブ:法要を録画し、後日視聴できる。
【3.お供え、位牌、遺影の配置】
✅仏壇や塔婆を整え、お供え物を準備
✅春彼岸には「ぼたもち」、秋彼岸には「おはぎ」を用意
【4.インターネット環境のチェック
Wi-Fi環境を確認し、安定した接続を確保。
進行の流れ
【1.僧侶をオンライン手配する】
✅僧侶の読経をオンラインで依頼し、日程を決める
✅お布施はオンライン決済で対応(価格はサービスによる)
【2.家族が事前に準備を整える】
✅供物、お線香、服装の準備(オンラインでもマナーを大切に)
【3.法要の開始(オンライン配信)】
✅ZoomやGoogle Meetを使って法要を開始
✅僧侶が読経を行い、参加者は画面越しに手を合わせる
【4.お焼香や読経をリモートで実施】
✅各自でお焼香を行う(お香の種類は自由)
✅読経に合わせて家族全員でお経を唱える
【5.親族で故人の思い出を共有(オンライン座談会)】
✅法要の後、親族で思い出を語り合う
✅昔の写真や動画を共有(事前に注文してフォトアルバムを用意するのも◎)
【6.終了後、お礼の連絡や振り返り】
✅僧侶や参加者に電話・FAXでご挨拶
✅お布施のオンライン送金(祝儀袋の準備不要)
✅録画を共有し、当日参加できなかった親族にも供養の機会を提供
オンライン法事の注意点
✅服装のマナー:画面越しでもフォーマルな服装が望ましい(喪服がベスト)
✅供養の意味を忘れずに:オンラインでも心を込めて手を合わせる
✅法事のタイプを選ぶ:個別供養か合同供養かを事前に決定
✅埋葬や墓石の管理:オンライン法要とは別に、実際の墓参りも検討
春秋彼岸のオンライン法事は、遠方の家族や忙しい親族でも参加しやすい供養の方法です。
準備を整え、スムーズに進行すれば、従来の法要と変わらない心のこもった供養が可能になります。
陽岳寺のオンライン法要サービス(例)
✅定休日なしで受付(予約可能時間の係数調整あり)
✅法要の相場を考慮した適正価格
✅塔婆や仏具の注文・記入代行も対応可能
現代の生活スタイルに合わせた新しい供養の形として、オンライン法事を活用してみてはいかがでしょうか?
オンライン法事に必要なもの&おすすめサービス

春秋彼岸のオンラインの法事をスムーズに進行できるように適切なサービスを活用する事が重要です。
ここでは、オンライン法事を快適に行うための必要なものとおすすめのサービスを紹介します。
春秋彼岸のオンライン法事(読経サービスリモート法要)
オンライン法事では、実際にお寺に足を運ばずとも、自宅にいながらお寺の僧侶の読経を受ける事が出来ます。
現在、多くのお寺がオンライン対応しており、Zoom、そしてYouTubeライブを利用した法要サービスを提供しています。
おすすめのポイント:
✅全国どこからでも僧侶の読経を受けられる
✅自分の都合の良い時間に予約が可能
✅春秋彼岸の特別供養としても利用できる
例えば、「お寺のリモート法要」では、Zoomを使ったライブ配信の読経サービスを提供しており、法要の時間に合わせて家族全員で本堂からの読経を聞く事が出来たりします。
オンライン法事は葬儀後の供養や四十日法要などにも適用できるため、従来の風習を大切にしながらも柔軟に法要を行う事が可能です。
法事用のZoom背景テンプレート
オンライン法事では、背景を整える事で厳かな雰囲気を演出出来ます。
最近では、仏事に適したZoom背景テンプレートが無料または有料で提供されており、仏壇のある空間を再現する事も可能です。
おすすめの背景例:
✅和室風の背景(仏壇がある和室のイメージ)
✅寺院の内観を模した背景(秋の彼岸会にも最適)
✅シンプルで落ち着いたデザイン(淡い色合いの背景で自然な雰囲気を演出)
Zoomのバーチャル背景機能を活用する事で、部屋の生活感を隠し、より厳かな雰囲気を作る事が出来ます。
オンラインで決済できる僧侶手配サービス
オンライン法事を行う際には、僧侶へのお布施をオンラインで送金できると便利です。
現在、多くのオンライン読経サービスでは、クレジットカード・銀行振込・QR決済など、多様な支払い方法に対応しています。
おすすめサービスの特徴:
✅事前にオンラインで僧侶を手配できる(受付時間は年中対応のものも)
✅クレジットカードや電子決済で簡単にお布施を送れる
✅春秋彼岸の特別法要プラン(合同法要・個別供養どちらも選べる)
例えば、「〇〇オンライン法要サービス」では、予約から決済までをオンラインで完結できるため、遠方にいる家族でも簡単に手続きを行う事が可能です。
また、お布施の「返し」についてもオンラインで相談できるため、手間を省きつつ供養のマナーを守る事が出来ます。
YouTubeライブを使った無料配信方法
YouTubeライブを活用する事で、無料でオンライン法事を配信する事が出来ます。
特に、親族の人数が多い場合や、当日参列できない人のために録画を残したい場合に便利です。
YouTubeライブを活用するメリット:
✅参加者はURLをクリックするだけで視聴可能(地域を問わず参加OK)
✅法要の様子を録画し、後日視聴できる(遠方の親族も安心)
✅公開範囲を限定すればプライバシーも保護できる
配信の手順:
1.YouTubeアカウントを作成し、「ライブ配信を有効化」する
2.配信の開始時間を設定し、家族や親族にURLを共有
3.僧侶の読経をライブ配信し、参加者が自由に視聴できるようにする
4.録画を保存し、後から供養の様子を見返せるようにする
この方法を使えば、春秋彼岸のオンライン法事を手軽に多くの人と共有する事が可能です。
よくある質問(Q&A)
Q1. オンライン法事の際に起こりやすい問題は?
オンライン法事では、以下のような問題が起こる可能性があります。
✅通信トラブル:事前にWi-Fi環境をチェックし、安定した回線を確保。
✅操作に不慣れな親族がいる:事前に電話やLINEで接続テストを行う。
✅僧侶の手配が間に合わない:早めに予約し、具体的な流れを確認する。
オンライン法事をサポートするサービスの活用
当社では、オンラインでの春秋彼岸の供養をサポートする各種サービスを提供しています。
サービスの特徴
✅僧侶のオンライン手配(四十日法要や年忌法要にも対応)
✅法事の進行をサポート(当日のトラブル対応)
✅供物や塔婆の注文受付(事前に記入して発送可能)
✅オンライン決済対応でお布施の送金が簡単
✅お問い合わせ専用番号を設置(電話やFAXでも相談可)
オンライン法事は新しい供養の形として、多くの方にとって便利な選択肢になりつつあります。
しかし、準備や進行には慣れが必要なため、プロのサポートを受ける事でスムーズに進める事が可能です。
まとめ:オンライン法事のメリットと活用法
✅遠方の家族も気軽に参加できる(移動の負担なし)
✅高齢者や体調が優れない方も自宅から供養できる
✅葬儀後の法要や年忌法要にも対応可能
✅YouTubeライブやZoomを活用し、供養の記録を残せる
✅僧侶の修行や風習を尊重しつつ、新しい供養の形を実現
時代の変化に合わせた供養の形として、オンライン法事をぜひご活用ください。
家族がつながる大切な時間を、心を込めて過ごしましょう。

